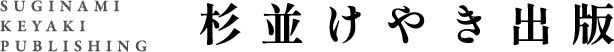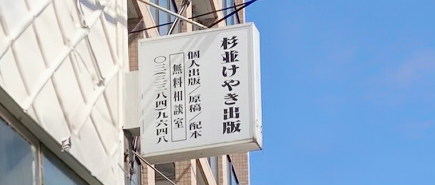文化省が管理をする「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」から、弊社で過去に出版した本が「授業目的公衆送信補償金制度」補償金の対象になっている、との連絡が入りました。
平たくいうと「あなたの書籍が、大学などの教育機関でインターネットを使用した授業で使用されたため、著作権利者へ補償金を支払います」という著作権法35条に基づく法律です。
今回、大学などの教育機関で多くの人(今回は250名以上)に本(DVD)が使われたということは、私たちとしても非常に嬉しい事実です。
ところで、「授業目的公衆送信補償金制度」をご存知でしょうか。
2018年5月の法改正で創設された、著作権に関する比較的新しい制度です。
教育分野の書籍を出版される方にとって関わりのある制度ですが、
どのような制度なのか、今回の件を通して分かりやすくお伝えします。
- 授業目的公衆送信補償金制度とは?
- 一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)
1.授業目的公衆送信補償金制度とは?
授業目的公衆送信補償金制度とは、
著作権法35条に基づき、一定の要件を満たす限り授業における著作物の公衆送信(インターネット送信等)利用を無許諾で行うことができる代わりに、当該利用をする教育機関の設置者(教育委員会や学校法人等)が指定機関に補償金を支払い、同補償金を当該利用に係る権利者へ分配する制度です。
平たくいうと「あなたの書籍が、大学などの教育機関でインターネットを使用した授業で使用されたため、著作権利者へ補償金を支払います」という著作権法35条に基づく法律です。
書籍(CD,dvdなど)使用した学校法人は、法律に基づき文化庁指定の団体・SARTRAS/サートラス(以下、サートラス)へ補償金を支払う義務がありますが、その数%は著作権利者である著者へ分配されます。
2.(一社)授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)とは?
先日、この制度の管理をする機関から1通のメールが届きました。
内容としては、「弊社で出版された本が、ある教育機関でインターネットを通して使われたため、著作権利者に補償金が発生しているため、著者へ連絡をしたい」という旨のメールでした。
「著作権利者」とはもちろん著者ですが、書籍には個人情報が掲載していないことが多いため、直接連絡が取れないため出版社へ取り次ぎ希望の連絡が来るということです。
そのため、基本的には出版社側では著者にその連絡が入っていることを伝え、その後のやりとりは著者の判断で行われます。
突然こんなメールが来たら、本当かなと一旦疑いたくなるものです。
昨今スパムメールや詐欺まがいのメールも非常に多く、信憑性をしっかりチェックすることは必須となっています。
私たちも信頼できる機関からのメールかどうかを調べた上で、文化庁公認の一般社団法人であることが確認できたため、資料を送ってもらうよう手配をしています。
送られてきたファイルは以下の通りです。
- 補償金の受領委任確認書(Word)
- 授業目的公衆送信補償金の分配に係る 権利者探索に関するご協力のお願い (PDF)
- 権利放棄(寄付)申込書 (PDF)
- 権利者探索フォーマット(Excel)
3.教育に関わる出版の可能性
弊社は特に教育に関わる出版が多いわけではありませんが、このように大学などの教育機関で多くの人(今回は250名以上)に届いた、役に立っているという事実は、大きな喜びとなりました。
参考文献
文化庁「授業目的公衆送信補償金の額の認可について」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92728101.html
一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会 サートラス
https://sartras.or.jp/seido/