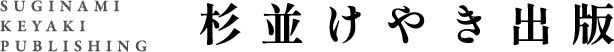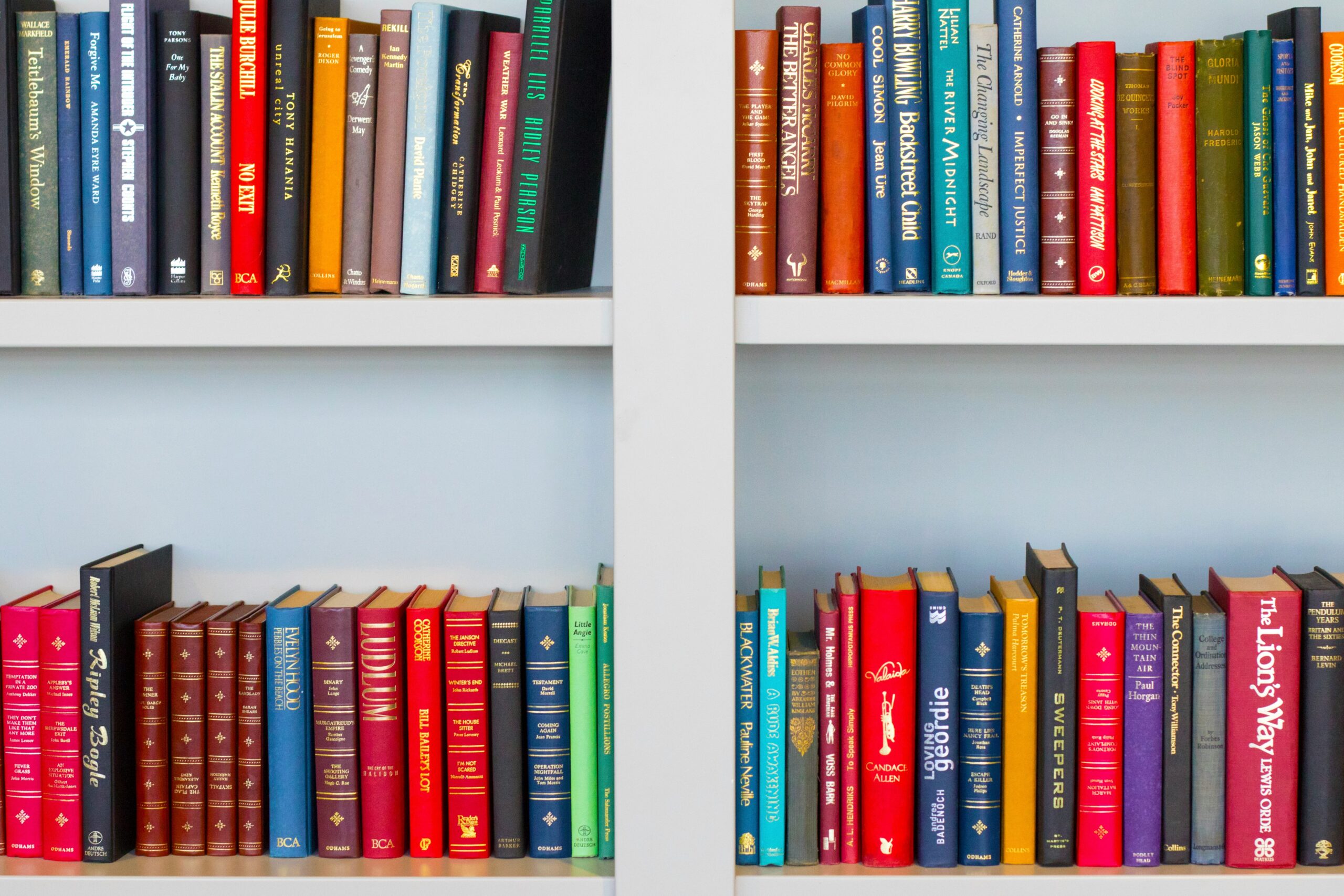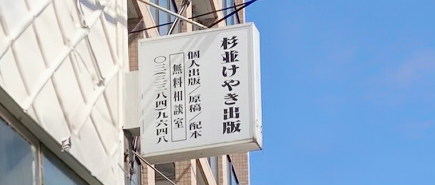本はどのような工程を経てできるのでしょうか?
原稿づくりのポイントや「制作の流れ」をご説明いたします。
1.企画・編集
担当/著者、編集者
どんな本を作るのかを明確にして、全体の構成を作ります。本を書く場合、多くの方は、いきなり原稿を書き始めるものですが、その前にこの企画構成をしっかり行うことをお勧めします。どのような内容をどのような順序で、どれくらいのボリュームで展開していくか、小説や自分史であれば、物語のあらすじを作ったり、全体の目次構成を作りはじめ、全体像のイメージやボリューム感を掴みします。
こうした全体像のイメージがあるのとないのとでは、その後の作業の進み具合が大きく違います。
2.原稿作成
担当/著者、イラストレーター、カメラマン、編集者
決定した構成内容に沿って、原稿を作ります。原稿は文字(テキスト)だけとは限りません。イラストや写真、図、表なども、必要に応じて用意します。実用書などでは図やイラストを多用することが多く、原稿を書き進めていく中で追加したくなることも少なくありません。
ですが自分で描き起こすならともかく、外部のイラストレーターに発注するのであればコストの増加や納期の延長にも直結します。それだけに「企画・構成」の段階で充分に検討しておくべきでしょう。なおテキスト・画像それぞれ、目的通りのものができているかどうかは、編集者が管理します。
なお文字原稿については、この段階で「素読み」を行うことが一般的です。著者の原稿を編集者がチェックして、明らかな誤りや修正が必要な部分をチェックするのです。特に郷土史など歴史を扱うものについては、年号の誤りなどを防ぐために裏取りが必要な場合もあります。
こうして内容の客観性を高めるとともに、これ以降の原稿の修正を少なくしていきます
3.紙面設計の確定
担当/著者、編集者、装丁デザイナー
本の体裁を決定します。体裁とは、いわば「本のかたち」と考えれば良いでしょう。判型(大きさ)、ページ数、本文の組み方、製本のしかた、表紙やカバーのデザイン、さらには使用する用紙など、本をかたちづくるすべての要素を指します。これは本の性格によって、それこそ星の数ほどの種類があります。
通常は本の内容や性格、読者層、流通形態、著者の意向などを踏まえた上で編集者とデザイナーとで検討して作り上げるのが常です。
ただし自費出版では、著者の意向が大きく反映されることが多いため、出版社側は希望があれば積極的に提案しています。
もちろん、すべての希望がかなえられるわけではありません。本としての体裁、品位、流通上の制約や耐久性などの制約があるからです。
4.組版(くみはん)
担当/デザイナー、組版オペレーター
原稿が揃ったところで、実際の紙面デザインを作っていきます。組版とはすでに決定した体裁の通りに、紙面を作っていく作業を指します。現代の組版はほぼコンピューター上での作業になりますので、文字や写真、手描きのイラストなどの原稿はすべてデジタルデータに変換され、パソコン上で組み上げられていきます。
近年ではパソコンの普及とともに、文字はもちろんイラストや写真などもすべてデジタルデータの状態で出版社に持ち込む方が増えています。データ変換の手間が省けますし大きなコスト削減にもつながりますので、お勧めの方法です。ただ、出版社によってどのようなデータにすれば良いかが微妙に異なります。データ入稿をお考えの方はまず担当編集者に相談すると良いでしょう。
5.カバー制作
担当/装丁デザイナー、イラストレーター、カメラマン、編集者
表紙やカバーの実際のデザインワークを行います。必要であればイラストや写真を新たに作り、それを素材としてデザイナーが製作します。製作中は編集者が細かな指示を出して、理想に近いものを作り上げていきます。
また表紙カバーの外側に巻き付ける「オビ」(腰帯とも言う)というものもありますが、これは書籍の広告ともいえるものですので通常は編集者が文言を作ります。ですが最近では、表紙カバーとのデザイン上の融合を図ったり、トレーシングペーパーなどの特殊紙を使ったりして人目をひこうとするケースが多いようです。
別紙を使わず、表紙カバーにオビを印刷してしまう、というやり方もあります。
6.校正
担当/著者、校正者、編集者、デザイナー
表紙、カバー、本文など、本の形にデザインしたものをプリンターで出力し、内容を確認します。誤字や脱字がないか、不適切な表現はないか……等々、あらゆる角度からチェックします。専門の校正者に依頼することもありますが、多くは編集者と著者による確認で対処しています。
画像やイラストについては、刷り色の濃淡や色のバランス、トリミングは適正かなどをチェックします。
7.印刷
担当/印刷所、編集者
何度かの校正を経て、問題がなければ印刷に移ります。通常は印刷所に一任して、印刷サンプルを校正として確認する形をとります。
ですが画集や写真集など、印刷の善し悪しが本の善し悪しに直結するような場合には、編集者はもちろんカメラマンやイラストレーターなどが印刷に立ち会い、細かな確認と修正を入れるケースもあります。
8.製本
担当/製本所
製本のしかたにはいくつかの種類がありますが、一般的な製本法ならばほとんどの製本所で対応できます。ただし、自費出版は少部数であることが多く、また著者自身の意向が大きく反映されるため、「凝った製本にしたい」と要望されることが少なくありません。
そうした場合には、製本サンプルを作るなどの作業も必要となります。
9.著者への納本、流通配本
担当/製本所
でき上がった本を著者に引き渡し、流通に乗せます。全国に流通させるときは「取次会社」という本専門の仲卸業者を通します。出版社によっては自前の直営書店を持ち、そこで販売したり、独自の流通網を使って流通させたりします。
いかがでしたか?
以上が、おおよその本作りの工程です。本の内容によって変わってくるところもありますが、これが一般的な流れだと考えて差し支えないでしょう。